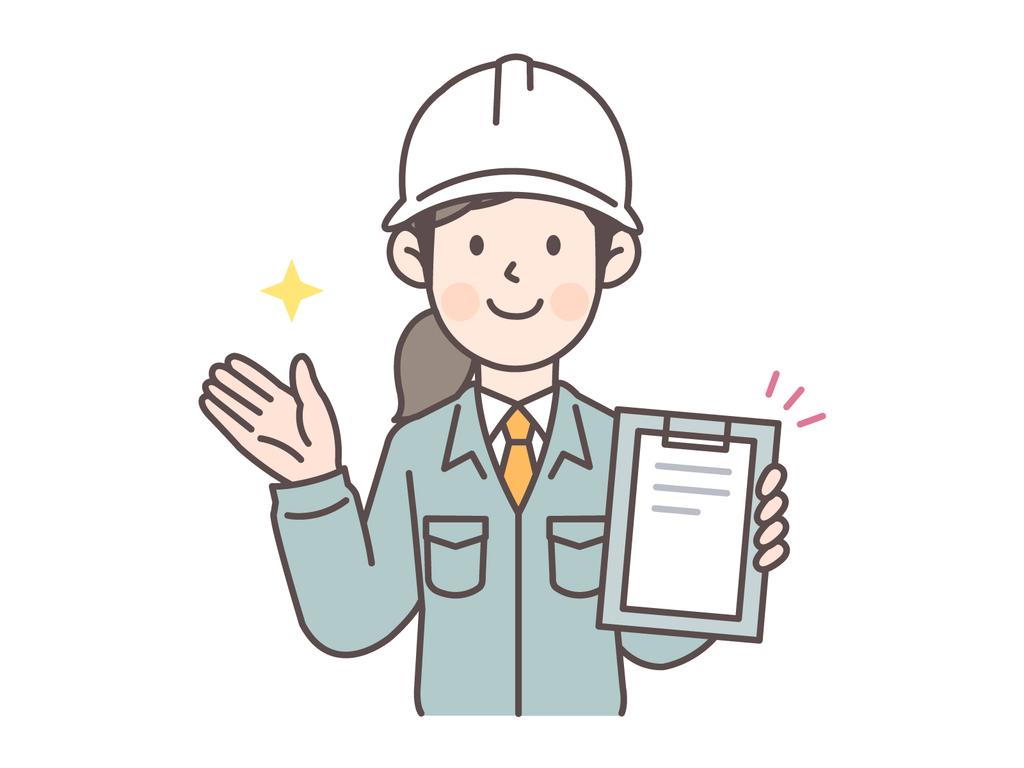一人親方と働き方改革!一人親方の今後について
「フリーランス」という単語が一般的に使われるようになって10年以上になります。
フリーランスとは、組織や団体に所属せず仕事を請け負う人や働き方を指す言葉です。
一方、建設業界では昔から「一人親方」という働き方が一般的でした。
一人親方は、従業員を雇用せずに、自分のスキルを持つ職人として自由に仕事をする人のことを指します。
会社に縛られず、自分の時間や仕事のスタイルを自由に選択できるこの働き方は、多くの職人にとって魅力的な選択肢でした。
しかし、現在、この働き方が変化の兆しを見せています。
2024年4月から建設業も時間外労働の規制が強化されます。
一人親方建設業共済会3つの特徴!

年会費6000円の
一人親方団体
- 2,000年4月設立以来の年会費6,000円
- 更新手数料無料 年会費のみ
- 労働保険事務組合が運営

最短翌日から加入可能!
加入証明書即日発行
- 簡単に加入可能!
- WEB、FAX、郵送、来所対応!
- 社労士賠責加入済み

3人の社会保険労務士常駐!
社労士賠責保険加入済
- 労災事故の安心!
- 労災請求の事務手数料一切なし
- 社会保険労務士報酬無料
一人親方とは
一人親方とは、建設業界において個々の建設プロジェクトや工事に自己の労働力のみを提供し、他の従業員を雇用しない個人事業主のことを指します。
これらの個人事業主は、法的には労働者に該当しないため、労働者保護の対象外となりがちですが、実際の作業現場では従業員と変わらない重要な役割を担っています。
一人親方の定義
一人親方は、自らが直接的に工事を請け負い、現場での施工を行う人物であり他の労働者や従業員を雇用しない点が特徴です。
主に個人が開業しており、建設業法に基づいた建設業の許可を得て事業を行っている人を指します。
一人親方のケース
1つの企業から仕事を受けている
足場設置など、一人親方だけでは完了できない仕事が多い業種では、このパターンがよく見られます。
また、彼らは元請けから提供される材料を使用するため、事実上、企業の一員として働いていると言えます。
複数の企業から仕事を受けている
大工や建築関係など、自分のスキルだけで仕事を遂行できる業種において、このパターンはよく見られる、自営業者のような状態にある一人親方のケースです。
一人親方と一口に言っても、これら2つのパターンのどちらに該当するかによって、今後の働き方が大きく異なりますし、将来のビジョンによっても、
進むべき方向が変わってくることでしょう。
建設業における役割
建設業界において一人親方は、専門的な技能や技術を持ち、特定の工程や作業を受け持つ重要な存在です。
多くの場合、電気工事、配管工事、塗装、内装仕上げなど、特定の専門分野を有しており、その技術力がプロジェクト成功の鍵を握ることも少なくありません。
しかし、一方で彼らは労働保険や社会保険の適用外となるケースが多いため事故や病気等で働けなくなった際の保障が不十分な状況にあります。
少しでも早く・安い会費で保険加入したい一人親方の皆様へ
一人親方建設業共済会は、国家資格を持つ社会保険労務士が国の保険を扱うから安心です!お急ぎの方でも安心してご加入いただける以下の強みがあります。
1
業界最安水準の年会費6,000円
2
加入証明書を最短即日発行!最短でお申込みの翌日から加入できます。
3
専門の社会保険労務士が常駐。労災事故でも安心手続き!
労災保険の特別加入を扱っている組合や団体は、当団体以外にもございます。ただし、親方様が加入されるときには次のポイントを確かめてから加入を決めるようにしてください。
- 会費が安くても、労災申請をするときや、証明書の再発行時に「別途費用」を請求する組合や団体があります。
- 更新時に「更新料」が毎年必要になる組合や団体もあります。
- 安くても労災保険に関する知識や経験が浅く、手続きや事故対応に不慣れな組合や団体もあります。
建設業にも働き方改革の波が押し寄せる
時間外労働の上限規制は、2018年に公布された働き方改革関連法に伴い、労働基準法が改正され設けられたもので、これまで「36協定はあるものの上限は青天井だった時間外労働に罰則付きで上限を設ける」という内容です。大企業では2019年4月から、中小企業でも2020年4月から施行されています。
労働基準法では「1日8時間・1週間40時間」を上限とする法定労働時間が定められており、この枠を超えた残業は法定時間外労働にあたります。法定時間外労働は、36協定を締結することで可能となりますが、今回の改正で、原則として「月45時間・年間360時間」までとなり、臨時的・特別な事情がない限りこれを超えることはできなくなりました。また、臨時的・特別な事情があって労使が合意した場合でも、次の時間を上回らないようにしなければなりません。
<特別な事情がある場合の「特別条項」でも守るべき上限>
1.年720時間(月平均60時間)
2.年720時間の範囲内で、
- ①2〜6ヵ月の平均でいずれも80時間以内(休日出勤を含む)
- ②単月100時間未満(休日出勤を含む)
- ③原則(月45時間)を上回る月は年6回を上限
建設業にも働き方改革の波が押し寄せています。建設業のみならず、他業種でも「2024年問題」として取り上げられることも多くあるように、2024年4月からは新しいルールのもとで運用しなければなりません。
建設業では、これまで法令の適用が猶予されていたため、36協定さえ結べば制限なく残業させても労働基準法違反にはなりませんでした。しかし2024年4月以降は、建設業においても、一般企業と同様に上記の上限ルールを守らなければならなくなります。(ただし、災害の復旧・復興の事業に関しては、時間外労働と休日労働の合計について「2〜6ヵ月の平均でいずれも80時間以内」「単⽉100時間未満」は適用されません)
この規制に違反すると、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が課せられます。罰則を受けると、労働基準法を違反した企業として以後の公共工事の受注などにも影響するため、上限を上回らないよう労働時間を正確に管理することが求められます。
一人親方制度は廃止される?
結論を述べると、一人親方を廃止するという議論は行われていません。
一方で「一人親方という制度が廃止されるのではないか」、といった噂が広がっています。実際に一人親方をされている方の中には、不安に思う方もいるのではないでしょうか。
このような噂の背景には、偽装一人親方問題や、インボイス制度などがあります。
偽装一人親方問題(労働者と評価すべき一人親方)
いわゆる「偽装一人親方」とは、実質的に労働者と評価すべき一人親方のことです。
労働者は、労働基準法や労働契約法などの労働法令によって保護されています。
これに対して、一人親方の場合は、企業(発注者)と対等な立場で契約を締結するため、原則として労働者に該当しません。
したがって、一人親方には労働法令が適用されず、社会保険・雇用保険・労災保険への加入義務も適用されないのです。
労働者を雇用する場合に比べると、一人親方に業務を発注する場合には、発注者にとって報酬以外のコストを抑えられるメリットがあります。
コストを抑えて労働力を確保しようとする企業は、形式的には一人親方(業務委託・請負など)として契約を締結しつつ、実質的には労働者のような働き方をさせることを「偽装一人親方」といいます。
一人親方にとってのインボイス制度
「インボイス制度」とは、税率が複数あっても、事業者の方が消費税を正確に納めていただけるように、消費税の金額等を書いた請求書・領収書等(インボイス)を基に計算する仕組みです。
この制度では、インボイス制度の下では、売手(下請業者)は買手(元請業者)に対して、正確な消費税額などを伝えるためインボイス(適格請求書)を交付しなくてはなりません。
買手(元請業者)としては、インボイスを保存しておくことで、消費税の仕入額控除を受けることができるようになります。
インボイスを発行するのは、適格請求書発行事業者のみです。適格請求書発行事業者になれるのは、消費税を納める事業者に限定されています。
元請業者としては、インボイスを発行できない業者と取引をすると仕入額控除を目的に、インボイスが発行できる業者との取引を優先することが考えられます。適格請求書発行事業者にならない場合、一人親方としての仕事が減ってしまう可能性があります。
中小建設業事業主の特別加入制度 3つの特徴!

業界最安水準
年会費36,000円
- 2000年以来の年会費業界最安水準
- 更新手数料無料 年会費のみ
- 労働保険事務組合が運営

最短翌日から加入可能!
加入証明書即日発行
- 簡単に加入可能!
- WEB、FAX、郵送、来所対応!
- 社労士賠責加入済み

3人の社会保険労務士常駐!
社労士賠償責任保険加入済
- 労災事故の安心!
- 労災請求の事務手数料一切なし
- 社会保険労務士報酬無料!
特別加入の手続き
中小事業主↗
労働保険事務組合を通じて「特別加入申請書(中小事業主等)」 を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し 、その承認を受けることになります。
※労働保険事務組合は全国に9,224団体あります。(令和4年3月現在)
一人親方 ↗
特別加入団体を通じて「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
※特別加入団体は全国に3173団体あります。(令和2年現在)
お問い合わせ・お申込み
- ※元請工事のない事業所のみとさせていただきます。元請工事がある事業所はお受けすることができません。
- ※雇用保険関係の手続きは原則行っていません。ご相談ください。
- ※社会保険労務士報酬は、いただきません。
- ※会費を安くしていますので、一括払いのみとさせていただきます。
インボイスを発行する権限は、適格請求書発行事業者にのみ与えられます。
適格請求書発行事業者となるには、消費税を納める事業者に限定されています。
元請業者としては、インボイスを発行できない業者との取引よりも、仕入れ額控除を目指して、
インボイスが発行できる業者との取引を優先するようになるでしょう。
適格請求書発行事業者にならない場合、仕事の減少が懸念されます。