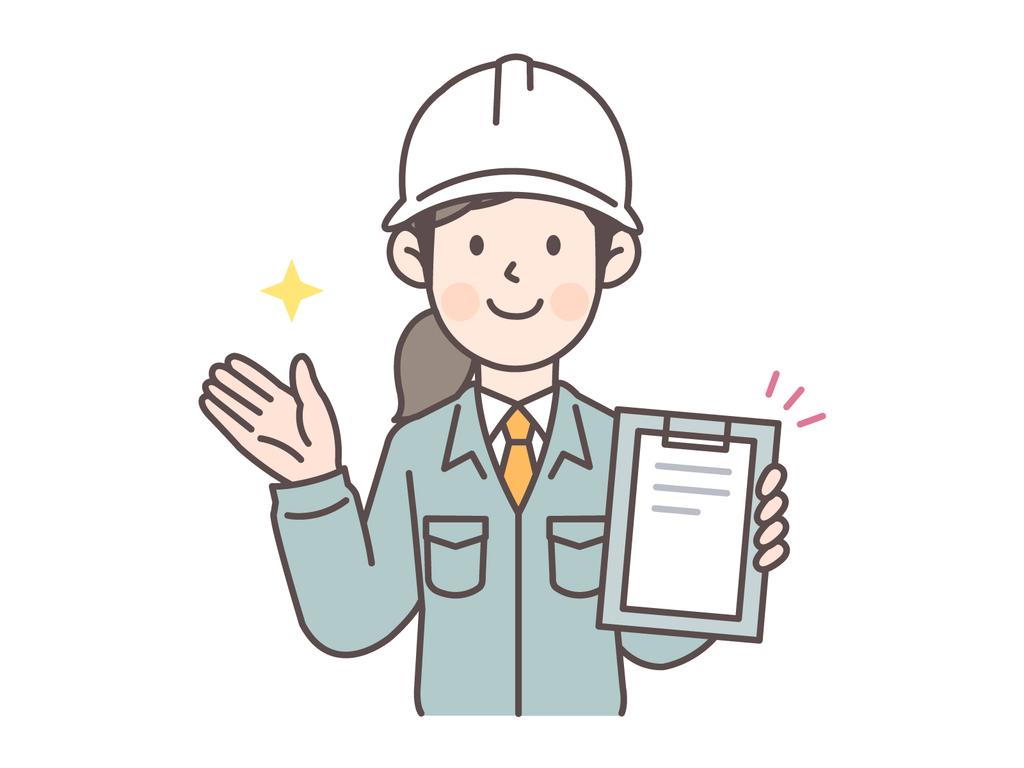一人親方から中小事業主まで!労災保険特別加入制度のすべて
建設業の一人親方などの自営業者は、労働者ではないため、労災保険の対象にはなりません。
しかし、特別加入団体や労働保険事務組合を通じて特別加入することが可能です。
労災に加入すれば、業務上や通勤途上の災害に遭っても治療費の負担がなく、休業補償も受けられます。
中小建設業事業主の特別加入制度 3つの特徴!

業界最安水準
年会費36,000円
- 2,000年設立以来の業界最安水準の年会費
- 更新手数料無料 年会費のみ
- 労働保険事務組合が運営

最短翌日から加入可能!
加入証明書即日発行
- 簡単に加入可能!
- WEB、FAX、郵送、来所対応!
- 社労士賠責加入済み

3人の社会保険労務士常駐!
社労士賠責保険加入済
- 労災事故の安心!
- 労災請求の事務手数料一切なし
- 社会保険労務士報酬無料
労災保険特別加入制度とは
労災保険特別加入制度の概要
労災保険特別加入制度は、通常の労災保険の対象にならない一人親方や中小事業主、自営業者などが任意で加入できる制度です。この制度により、業務中や通勤中に起きた事故や災害による負傷・疾病などに対して補償が受けられます。特別加入は労働者としての地位を持たない人々に対する救済措置として設けられており、特に建設業や農林水産業、自動車運送業など高い労働リスクを伴う職業における安心を提供します。
労災保険の本来の仕組みと特別加入の背景
労災保険は本来、労働者を対象とし、業務や通勤中に発生した災害に対して医療費や休業補償、障害補償などを提供する制度です。しかしながら、自営業者や中小事業主、一人親方などは労働者とはみなされず、通常の労災保険の対象外となります。この背景には「自己責任で働く」という観点がありますが、職場環境や労働条件によってリスクは決して軽視できません。そのため、こうした人々を保護するために「特別加入制度」が制定されました。この制度は、労災保険法に基づき、申請を通じて加入が認められる仕組みとなっています。
対象となる人・事業の範囲
特別加入制度の対象となるのは、、大きく4種類に区分されます。
| 区分 | 対象者 |
| 中小事業主等 | 次の①、②にあたる方(※) 1 一定の労働者を常時使用する事業主 2 労働者以外で①の事業主の事業に従事する人(事業主の家族従業者など) |
| 一人親方その他の自営業者 | 労働者を使用せず一定の事業を行うことを常態とする一人親方その他の自営業者およびその事業に従事する方 |
| 特定作業従事者 | ① 特定農作業従事者 ② 指定農業機械作業従事者 ③ 国または地方公共団体が実施する訓練従事者 ④ 介護作業従事者および家事支援従事者 ⑤ 労働組合等の一人専従役員 ⑥ 芸能関係作業従事者 ⑦ アニメーション制作作業従事者 ⑧ ITフリーランス等 |
| 海外派遣者 | ● 日本国内の事業主から、海外で行われる事業に労働者として派遣される人 ● 日本国内の事業主から、海外にある中小規模の事業に労働者ではない立場として派遣される人 ● 開発途上地域に対する技術協力の実施の事業 (有期事業を除く)を行う団体から派遣され、開発途上地域で行われている事業に従事する人 |
(※)1年間に100日以上労働者を使用している場合は、常時労働者を使用しているものとして扱われます。
(※)中小事業主等と認められる企業規模は、金融業・保険業・不動産業・小売業は労働者数50人以下、卸売業・サービス業は100人以下、その他業種は300人以下です。
- 自身の業務に積極的に従事している一人親方や事業主等。
- 家族従事者や法人役員であり、会社などの業務と密接に関わる者。
- 労働者を1人以上雇用し、法律で定められる中小事業主の基準を満たしている事業主等。
- 一定期間以上にわたり海外で業務を行う派遣労働者。
業種に関しても建設業、自動車運送業、漁業、農業、林業など、業務上の事故リスクが高い業界が主な対象となっています。
少しでも早く・安い会費で保険加入したい建設業の中小事業主の皆様へ
当労働保険事務組合は、国家資格を持つ社会保険労務士が国の保険を扱うから安心です!お急ぎの方でも安心してご加入いただける以下の強みがあります。
1
業界最安水準の年会費36,000円(入会金10,000円)
2
加入証明書を最短即日発行!最短でお申込みの翌日から加入できます。
3
専門の社会保険労務士が常駐。労災事故でも安心手続き!
労災保険の特別加入を扱っている労働保険事務組合は、当団体以外にもございます。ただし、親方様が加入されるときには次のポイントを確かめてから加入を決めるようにしてください。
- 会費が安くても、労災申請をするときや、証明書の再発行時に「別途費用」を請求する組合や団体があります。
- 更新時に「更新料」が毎年必要になる組合や団体もあります。
- 安くても労災保険に関する知識や経験が浅く、手続きや事故対応に不慣れな組合や団体もあります。
一人親方が特別加入制度を利用するメリット
一人親方とは?その働き方とリスク
一人親方とは、特定の雇用主を持たず、自ら事業を営む個人事業主のことを指します。特に建設業や運送業などで広く見られます。一人親方は従業員を雇用せず、自ら作業を行うため、労働者としての保護が適用されず、労災保険に一般的に加入することはできません。しかし、業務中の事故や病気のリスクは雇用労働者と同等、あるいはそれ以上に高いことが特徴です。そのため、業務中の怪我や病気に対する補償が不十分である場合、生活そのものが脅かされる可能性があります。
特別加入制度を利用するメリットとカバー範囲
一人親方が労災保険の特別加入制度を利用することで、怪我や病気に対する補償を受けることが可能となります。特別加入制度のメリットは、業務中の怪我や災害に加えて、通勤途中の事故も補償対象に含まれる点です。また、休業補償や治療費の全額補償が受けられるため、万が一のリスクに備える上で非常に重要です。さらに、後遺障害が残った場合や、死亡時にも家族への補償が提供されるため、本人だけでなく家族にとっても安心できる制度といえます。
加入条件と手続きの流れ
一人親方が特別加入するための条件としては、まず対象業種であることが必要です。建設業や運送業、漁業など特定の業種が対象となります。さらに、実際に就労していることが確認できることも条件のひとつです。手続きは、近隣の労働保険事務組合を通じて行う必要があり、必要書類の提出や加入費用の支払いを経て加入が完了します。申請にあたっては、事務手続きを円滑に進めるために、専門家のサポートを受けるとスムーズです。
建設業における特別加入の重要性
建設業は一人親方が特に多い業界であり、作業環境も危険が伴うことが多いです。一人親方が労災事故に巻き込まれてしまうと、高額な治療費や休業中の収入減に直面することになります。そのため、建設業における特別加入制度の重要性は非常に高いといえます。特に中小事業主が関与する現場では、労働者全員の安全性を確保するだけでなく、一人親方が特別加入することで相互の信頼関係を築きやすくなる利点もあります。このように建設業を営む一人親方にとって、特別加入は安定した事業継続を実現する上で欠かせない仕組みといえるでしょう。
一人親方建設業共済会3つの特徴!

年会費6000円の
一人親方団体
- 2,000年4月設立以来の年会費6,000円
- 更新手数料無料 年会費のみ
- 労働保険事務組合が運営

最短翌日から加入可能!
加入証明書即日発行
- 簡単に加入可能!
- WEB、FAX、郵送、来所対応!
- 社労士賠責加入済み

3人の社会保険労務士常駐!
社労士賠責保険加入済
- 労災事故の安心!
- 労災請求の事務手数料一切なし
- 社会保険労務士報酬無料
中小事業主の特別加入制度の仕組み
中小事業主が特別加入できる業種と条件
労災保険の特別加入制度は、通常の労災保険では対象外となる中小事業主やその家族従業者などを保護するための仕組みです。中小事業主が特別加入できる要件として、業種と雇用形態に基づく制限があります。具体的には、金融業や不動産業、小売業は労働者数50人以下、卸売業やサービス業では100人以下、その他製造業や建設業などでは300人以下の事業規模が条件です。また、特別加入の申請には、労働者を1名以上雇用していること、労働者と同じ業務に従事していることが必要とされます。
常時使用する労働者数による制約
中小事業主が特別加入の対象となるか否かは、常時使用している労働者の人数が大きなポイントとなります。労災保険中小事業主等の特別加入とは、この労働者規模に応じた条件をクリアした場合に認められる制度です。具体的には、年間100日以上労働者を雇用している場合、"常時使用"と見なされます。ただし、家族従業者のみを雇用している場合は対象外となりますので注意が必要です。これらの制約は、中小事業主の実情に即した制度運用を実現するために設けられています。
特別加入の保証内容と基準
中小事業主が特別加入によって受けられる保証は、一般の労災保険加入者とほぼ同等の内容が提供されます。主な補償内容として、業務上の災害による治療費を全額負担する療養補償、休業4日目以降の給付基礎日額の80%を補償する休業補償、及び後遺障害が残った場合の補償があります。また、労災事故が原因で死亡した場合には遺族補償年金や葬儀費用(葬祭料)が支給されます。中小事業主の特別加入では、これらの保証内容が明確に定められており、業務に起因する災害リスクを包括的にカバーします。
法人役員や家族従業者の特例
法人役員や家族従業者も一定の条件のもとで特別加入の対象となります。法人の代表者だけでなく、法人役員が現場作業などの業務に従事している場合、その業務の特性に応じて加入が認められることがあります。さらに、家族従業者についても、労働者と同等の業務内容であれば特別加入の申請が可能です。ただし、これらの特例は、対象者が働いている実態に基づいて判断されるため、申請時に詳細な業務内容の記載や証明が求められるケースがあります。
特別加入制度の申し込み手順と注意点
労災特別加入を申請する方法
労災保険の特別加入を申請する場合、まず所属する業界団体や事業所が労働保険事務組合に登録しているか確認する必要があります。手続きは一般的に労働保険事務組合を通じて行われます。特別加入の申請にあたっては、「特別加入申請書」や「労災保険関係成立届」など必要書類を用意し、管轄の労働基準監督署または事務組合に提出します。これらの手続きは事務組合が代理で行うことで迅速化され、申請者の労力を軽減することが可能です。
必要書類と手続きを円滑に進めるコツ
特別加入の申請をスムーズに進めるには、あらかじめ必要な書類を正確に揃えることが重要です。主な必要書類は、特別加入申請書、事業内容を証明する書類(例えば事業概要書や登記簿謄本など)、労働者名簿、労働保険関係成立届などです。また、本人の事業への関与や業務従事を確認する資料も必要です。申請の際は、記載内容に誤りや不足がないか再確認し、事務組合に手続きの進行状況を随時確認することで、手続きの遅延を防止できます。特に、中小事業主が従業者を雇用している場合は、その従業者の労災保険加入状況の確認も肝心です。
手数料や加入費用の考え方
労災保険特別加入には、加入手続き費用が発生します。この手数料は、事務組合に対して支払う手数料と、加入する労災保険の保険料に分かれます。保険料は、年間の給付基礎日額に基づいて算出され、業種や事業内容によって異なる場合があります。中小事業主の場合、労働者の人数や従事する業務のリスクに応じて保険料が設定されるため、詳細な計算が必要です。事前に手数料と保険料を確認しておくことで、余計な費用トラブルを避けることができます。また、事務組合の利用によっていくらコスト削減が見込めるかを検討することも有益です。
事務組合への委託とそのメリット
労災保険特別加入の手続きは、労働保険事務組合に委託することが一般的です。事務組合を利用する最大のメリットは、複雑な書類作成や申請手続きを代行してもらえる点です。特に、労災保険に関しては法律や規定が多岐にわたるため、専門知識を持つ事務組合に依頼することで手続きの正確性が高まります。また、保険料の計算や更新手続きに関するアドバイスを受けられる場合もあり、中小事業主にとって手間を大幅に省ける点が魅力です。ただし、委託料が発生するので、その費用を事前に確認し、必要に応じて複数の事務組合と比較することが重要です。一部の事務組合は特別加入に特化したサポートを提供しているため、しっかりとしたサポート体制があるかを確認することもポイントです。
少しでも早く・安い会費で保険加入したい一人親方の皆様へ
一人親方建設業共済会は、国家資格を持つ社会保険労務士が国の保険を扱うから安心です!お急ぎの方でも安心してご加入いただける以下の強みがあります。
1
業界最安水準の年会費6,000円
2
加入証明書を最短即日発行!最短でお申込みの翌日から加入できます。
3
専門の社会保険労務士が常駐。労災事故でも安心手続き!
労災保険の特別加入を扱っている組合や団体は、当団体以外にもございます。ただし、親方様が加入されるときには次のポイントを確かめてから加入を決めるようにしてください。
- 会費が安くても、労災申請をするときや、証明書の再発行時に「別途費用」を請求する組合や団体があります。
- 更新時に「更新料」が毎年必要になる組合や団体もあります。
- 安くても労災保険に関する知識や経験が浅く、手続きや事故対応に不慣れな組合や団体もあります。
特別加入制度を活用する際の課題と注意点
特別加入で見逃しがちな保証の制約
特別加入制度は、中小事業主や一人親方に労災保険の保証を提供する有益な制度ですが、その内容を十分理解しないまま加入する場合、予期しない制約に直面することがあります。例えば、休業補償給付や遺族給付は一定の条件を満たした場合にのみ支払われるため、自分の業務内容や加入時の条件が実際に適合しているかを確認することが重要です。また、特別加入者が特に注意すべき点として、保証対象となるのは「業務災害」または「通勤災害」に限定されており、業務以外での怪我や死亡は基本的に補償の対象外となります。このような制約を理解することで、加入後のトラブルを防ぐことができます。
実際の事故時の申請手続きと対応
特別加入者が実際に労災事故に遭遇した場合、迅速かつ適切に申請を行うことが重要です。申請には、事故発生時の詳細や業務内容、事故との因果関係を示す資料が必要となります。特に、中小事業主や一人親方の場合、事故時に第三者の証人がいないケースも多いため、業務内容が労働に該当することを証明するための記録を日常的に残しておくことが推奨されます。また、申請に当たっては労働保険事務組合を通じて手続きを進めることが多いですが、この際も正確な情報を提供することが求められます。適切な対応が保証を受ける鍵となります。
更新忘れと加入期間によるトラブル防止策
特別加入制度では、一定の期間ごとに更新手続きが必要です。この更新を怠ると、有効な期間を過ぎてしまい、いざというときに保証を受けられなくなるリスクがあります。更新忘れを防ぐためには、更新期限が近づいた際に通知を受け取れるシステムを利用するか、事務組合を通して手続きを管理しておくのが有効です。また、更新手続きを行う際には、加入時の条件や保証内容に変更がないかを再確認することも重要です。
業務外での補償対象外のケース理解
特別加入の保証対象は、業務中の災害や通勤途中の災害に限定されています。そのため、プライベートな時間に発生した怪我や病気は補償の範囲外となる点に注意が必要です。特に、中小事業主が保証対象となるかどうかの境界は曖昧になりがちであり、例えば業務に関連しない私的な用事の際に起こった事故は補償の対象外とされることが一般的です。加入前にこうしたケースについて正確に把握することで、万が一補償を受けられなかった場合のリスク管理にも役立ちます。
特別加入の手続き
中小事業主↗
労働保険事務組合を通じて「特別加入申請書(中小事業主等)」 を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し 、その承認を受けることになります。
※労働保険事務組合は全国に9,224団体あります。(令和4年3月現在)
一人親方 ↗
特別加入団体を通じて「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
※特別加入団体は全国に3173団体あります。(令和2年現在)
お問い合わせ・お申込み
- ※元請工事のない事業所のみとさせていただきます。元請工事がある事業所はお受けすることができません。
- ※雇用保険関係の手続きは原則行っていません。ご相談ください。
- ※社会保険労務士報酬は、いただきません。
- ※会費を安くしていますので、一括払いのみとさせていただきます。