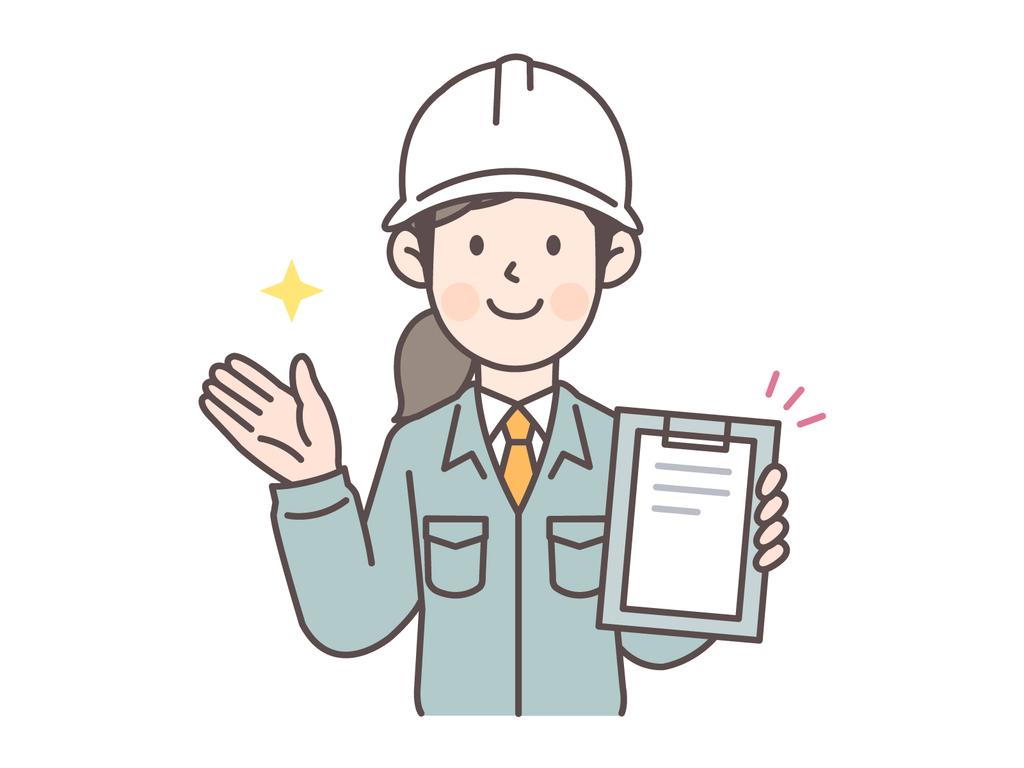経営者の皆さん!事業主や役員は政府労災保険を使いえない?
労災保険とは「労働者災害補償保険」の略で、労働者を対象にした保険制度です。労働者の労働災害によるケガ、障害、死亡をはじめ、作業や職場環境が原因でかかる病気、働き過ぎによる精神疾患など、仕事が原因で引き起こされる労働者の病気やケガに対して給付が行われます。通勤中の事故によるケガなども給付対象です。
つまり、労災保険とは、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷・疾病・障害又は死亡に対して労働者やその遺族のために、必要な保険給付を行う制度なのです。
この労災保険、事業主や役員、家族従事者の方は対象外なのです。ご存知でしたか?
中小建設業事業主の特別加入制度 3つの特徴!

業界最安水準
年会費36,000円
- 2,000年設立以来の業界最安水準の年会費
- 更新手数料無料 年会費のみ
- 労働保険事務組合が運営

最短翌日から加入可能!
加入証明書即日発行
- 簡単に加入可能!
- WEB、FAX、郵送、来所対応!
- 社労士賠責加入済み

3人の社会保険労務士常駐!
社労士賠責保険加入済
- 労災事故の安心!
- 労災請求の事務手数料一切なし
- 社会保険労務士報酬無料
そもそも労災保険とは
労災保険法は、この労働基準法の災害補償の規定を担保するための法律であり、同じ昭和22年に姉妹法として制定されました。
労災保険とは「労働者災害補償保険」の略で、労働者やその遺族の生活を補償するための公的な保険制度です。
本来、従業員を雇用する事業主には、労働基準法上の安全配慮義務があります。業務上の事故による傷病等が生じた場合、使用者に過失がなくても被災労働者や遺族に補償義務があります(労働基準法第8章「災害補償」)。
仕事中や通勤途中に、ケガや病気、障害、あるいは死亡となったときに、労働基準監督署から「労災認定」を受けることで、労働者(死亡時は遺族)にさまざまな保険給付がなされます。
保険料は事業主の負担で、労働者自身の負担はありません。
労災保険の適用対象者
原則として、常用、日雇、パート、アルバイト等、名称及び雇用形態にかかわらず、労働の対価として賃金を受けるすべての労働者が対象となります。
(ただし、船員保険の被保険者は適用がありません。)
適用対象外の法人の役員(取締役等)とは
下表を参照願います。
| 労災保険 | ||
| 適用者とならない者 | 適用者となる者 | |
| 株式会社 | 代表取締役定款又は取締役会の決定による業務執行取締役監査役 | 左記の1及び2以外の取締役で業務執行取締役の指揮監督を受けて労働に従事し、労働の対価として賃金を一般の労働者と同一条件で支払を受ける者。監査役の場合、上記1の取締役と同様の労働実態にある者。 |
| 有限会社※(注) | 全ての取締役監査役 | 代表取締役以外の取締役で、定款、社員総会、或いは取締役の過半数をもって、業務執行を除外された者であって、業務執行取締役の指揮監督を受けて労働に従事し、労働の対価として賃金を一般の労働者と同一の条件で支払を受ける者。監査役の場合、上記1の取締役と同様の労働実態にある者。 |
| 合名会社 | 全ての社員 | 定款により、業務執行を除外された社員で、業務執行社員の指揮監督を受けて労働に従事し、労働の対価として賃金を一般の労働者と同一の条件で支払を受ける者。 |
| 合資会社 | 全ての無限責任社員 | 有限責任社員定款により、除外された無限責任社員で、業務執行社員の指揮監督を受けて労働に従事し、労働の対価として賃金を一般の労働者と同一の条件で支払を受ける者。 |
| その他 | その他の法人及び法人格のない社団等の代表者 | 業務執行を除外された者で、規約、実態から労働関係にあると認められる者。 |
※(注)18.5.1 会社法施行→有限会社の廃止
既存の有限会社は会社法上の株式会社として存続。
ただし、現行の有限会社に関する規定の適用を受け続けることができる「特例有限会社」として存
続することも可能。
役員でも労災保険が適応可能になるケース
役員でも労災保険が適用されるケースがあります。
1.労働者性がある場合
役員の肩書があっても、実態として労働者と同様の働き方をしていると判断されれば、労災保険が適用されます。
- 業務執行権がない: 株主総会や取締役会で決定された事項を実行する権限がない。
- 労働の対償となる賃金を受けている: 労働に対して給与を受け取っている。
- 事実上の指揮監督を受けている: 上司や他の役員から指示を受け、業務を行っている。
2.特別加入制度を利用する場合
役員は原則として労災保険の対象外となるため、中小企業の事業主や役員などが「労災保険の特別加入制度」を利用することで労災保険に加入できます。
対象となる事故: 業務中の事故、業務上の病気などが補償の対象となります。例えば、外回り営業中の交通事故や、建設現場での作業中の負傷などが考えられます。
- 加入手続き: 労働保険事務組合等を経由して労働基準監督署へ特別加入申請書を提出することで加入できます。
- 中小事業主等: 中小企業の経営者や役員が、労働者に準じた保護を受けるために加入できます。
- 一人親方等: 建設業など、一人で事業を行っている方も、自身を労災保険の対象とするために加入できます。
特別加入の要件・加入申請の手続き
要件1 建設業を営む個人・法人の経営者とその家族
労災保険の特別加入制度は、雇っている労働者と同じように業務を行っている事業主の保護を目的とした、あくまで任意の保険制度です。中小事業主が労災保険に加入するためには、以下の条件を満たしている必要があります。
○建設工事の請負を営む経営者。
○兼業でも加入できます。
○法人の役員・個人事業主とその同居の家族従事者のみが労災の特別加入ができます。
要件2 従業員1名以上雇用している。(年間100日以上にわたって雇用している)
○従業員とは、建設現場に従事する現場作業員等の労働者を言います。
○法人の役員・個人事業主とその同居の家族は、従業員数から除きます。
要件3 労働保険事務組合に事務委託。
○労働保険事務を労働保険事務組合に委託する必要があります。
○特別加入申請書を労働保険事務組合経由で労働基準監督署へ提出しなくてはなりません。
○事業所が、単独で申請することはできません。
特別加入の手続き
中小事業主↗
労働保険事務組合を通じて「特別加入申請書(中小事業主等)」 を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し 、その承認を受けることになります。
※労働保険事務組合は全国に9,224団体あります。(令和4年3月現在)
一人親方 ↗
特別加入団体を通じて「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
※特別加入団体は全国に3173団体あります。(令和2年現在)
お問い合わせ・お申込み
- ※元請工事のない事業所のみとさせていただきます。元請工事がある事業所はお受けすることができません。
- ※雇用保険関係の手続きは原則行っていません。ご相談ください。
- ※社会保険労務士報酬は、いただきません。
- ※会費を安くしていますので、一括払いのみとさせていただきます。