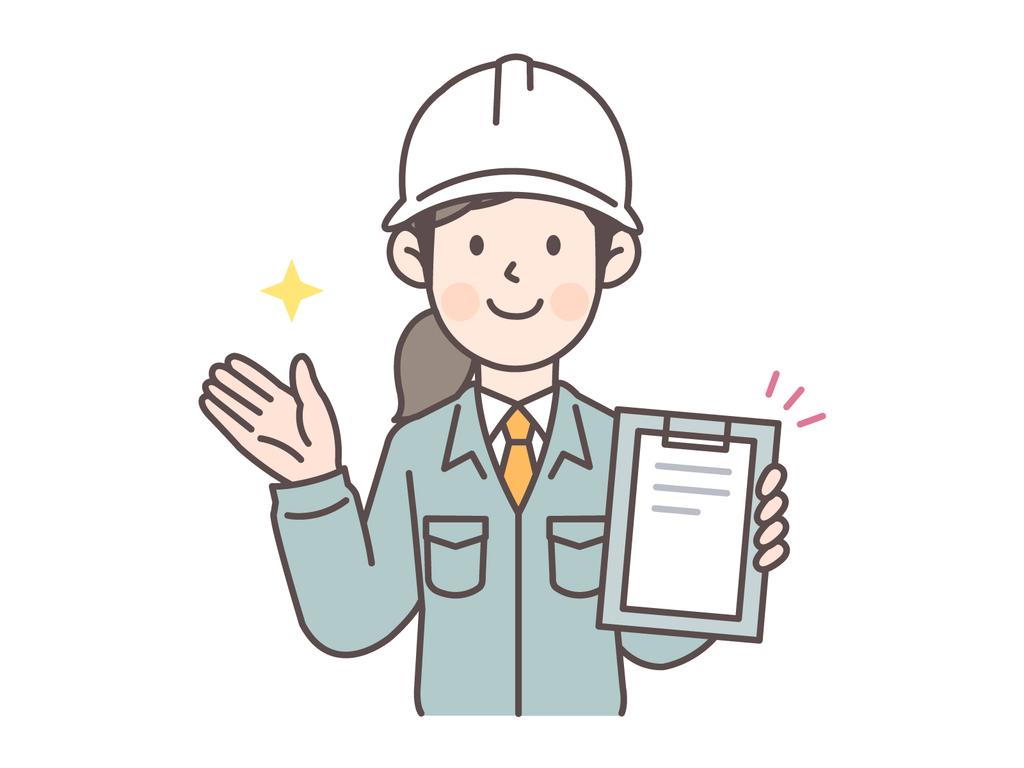一人親方か偽装か?知識を持って見極める方法を解説
偽装一人親方問題とは、本来は労働者として扱わなければいけない職人(技能者)などを独立させて、偽装請負の一人親方化が進む問題のことです。
偽装一人親方問題は、職人(技能者)の処遇低下や公正・健全な競争環境を阻害する大変重要な問題とされています。
一人親方建設業共済会3つの特徴!

年会費6000円の
一人親方団体
- 2,000年4月設立以来の年会費6,000円
- 更新手数料無料 年会費のみ
- 労働保険事務組合が運営

最短翌日から加入可能!
加入証明書即日発行
- 簡単に加入可能!
- WEB、FAX、郵送、来所対応!
- 社労士賠責加入済み

3人の社会保険労務士常駐!
社労士賠責保険加入済
- 労災事故の安心!
- 労災請求の事務手数料一切なし
- 社会保険労務士報酬無料
一人親方と個人事業主の主な違い
一人親方と個人事業主の主な違いは、雇用の有無と業種の範囲にあります。
一人親方とは何か
一人親方の定義と業種
一人親方とは、主に建設業や林業など特定の業種において、労働者を雇用せずに自ら業務を遂行する個人のことを指します。
一人親方は、自分自身または家族と共同で業務を行うことが一般的です。
この働き方は、一定の日数以上他人を雇用しないことが条件となっており、労働者を100日未満であれば一人親方と見なされます。
この制度は、独立した形で自由に働くことを望む職人や専門家にとって、柔軟な働き方を可能にする一方、業務に従事する際の保険や社会的な保障の面で自己責任が求められる特徴があります。
建設業で特別加入できる一人親方は、特に職種の限定はなく、土木、建築その他の工作物の建設・改造・保存・修理・変更・破壊もしくは、解体又はその準備の作業(設計・監理業は除く)に従事している方、及びその家族従業者です。
個人事業主との違い
個人事業主とは、法人ではなく個人で事業を営む自営業者を言います。
事業であるかどうかは、確たる基準があるわけではありませんが、次のような点について総合的に判断します。
- 反復、継続的な経済活動であるか?
- 利益を得ることを目的としているか?
- 自己の判断と責任で活動しているか?
- サービスや商品に対して相当の対価を受けているか?
独立・反復・継続して一定規模の仕事をしている場合は、その仕事は事業となり、個人事業主として仕事をしていることになります。会社員の副業であっても、これらの判断により事業かどうかが問われます。
少しでも早く・安い会費で保険加入したい一人親方の皆様へ
一人親方建設業共済会は、国家資格を持つ社会保険労務士が国の保険を扱うから安心です!お急ぎの方でも安心してご加入いただける以下の強みがあります。
1
業界最安水準の年会費6,000円
2
加入証明書を最短即日発行!最短でお申込みの翌日から加入できます。
3
専門の社会保険労務士が常駐。労災事故でも安心手続き!
労災保険の特別加入を扱っている組合や団体は、当団体以外にもございます。ただし、親方様が加入されるときには次のポイントを確かめてから加入を決めるようにしてください。
- 会費が安くても、労災申請をするときや、証明書の再発行時に「別途費用」を請求する組合や団体があります。
- 更新時に「更新料」が毎年必要になる組合や団体もあります。
- 安くても労災保険に関する知識や経験が浅く、手続きや事故対応に不慣れな組合や団体もあります。
偽装一人親方のリスク
偽装の背景と問題点
近年、建設業界などで「偽装一人親方」の問題がクローズアップされています。
これは、本来労働者として雇用されるべき人々が、一人親方として稼働させられるケースを指します。
このような偽装は雇用主が社会保険や労災保険の料率を回避する目的で行われることが多いですが、これには大きな問題があります。まず、労働者が社会保険や労災や雇用保険といった社会保険の恩恵を受けられず、賃金や労働条件も労働法で保護されないというリスクがあります。
この状況では正当に保護を受けることも難しくなり、労働者が不安定な状態に置かれてしまうのです。
労災保険と社会保険の影響
労災保険への加入は、事故や疾病の際に大きな助けとなります。
しかし、偽装一人親方の場合はこの加入が自己責任となり、実際に事故が発生した際に保障が得られない可能性があります。
また、社会保険未加入の状態が続くと、退職後や老後の年金給付にも影響が及びます。
一人親方としての立場を持続しながらも、労災保険や社会保険に関するしっかりとした知識を持ち、必要に応じて環境を調整することが重要です。
労災保険への加入方法や一人親方の見分け方などを理解することで、自己防衛することが求められています。
一人親方と個人事業主の比較
メリットとデメリット
一人親方と個人事業主は、いずれも独立して事業を行う形態ですが、目的や活動内容によってそのメリット・デメリットが異なります。
一人親方は主に建設業界で活躍しており、労災保険に特別に加入できる点が大きなメリットです。
特に、業界最安値の年会費6,000円で加入でき、加入証明書も最短即日で発行されるため、即座に仕事を始められるという利点があります。
しかし、労災保険は任意加入のため、加入していない場合、怪我や病気の際に十分な保障を受けられないリスクがあります。
一方、個人事業主はより広範な業務が可能で、従業員を雇うことができる自由さが魅力です。ただし、事業の成功や成長に伴う責任も増すため、その分リスクも大きくなります。また、社会保険や雇用保険の管理が必要になり、これらの手続きが負担となることもあります。
税制と保険制度の違い
一人親方と個人事業主の税制および保険制度にはいくつかの違いがあります。
一人親方の場合、特別加入制度を利用することで、労災保険に加入でき、業務中の事故や怪我に対する保障を得られます。
しかし、社会保険については個別に対応する必要があり、自ら健康保険や国民年金に加入しなければなりません。
このように、一人親方と個人事業主はそれぞれに異なる法律上の基準と保険の選択肢がありますので、自身の事業形態と活動内容に応じて、適切な判断を下すことが重要です。
見極めのポイントと実践方法
法的基準とガイドライン
一人親方の見分け方を正確に把握するためには、法的基準とガイドラインをしっかり理解することが必要です。
一人親方として認められるためには、労働者を雇用せず、特定の業種で事業を行うことが基本条件とされます。
特に建設業界においては、大工や電気工事士、塗装工、解体工、設備工事士などの職種が該当します。
法的には、労働者を使用しない日数が100日未満であれば、一人親方と認定される可能性があります。
また、一人親方特別加入の申請を行うことで、労災保険に加入することが可能です。
これらのポイントを押さえ、一人親方が適切に区別されることが、法的な基準に基づく見極めに役立ちます。
ケーススタディ: 実務での見極め例
一人親方を実務で見分けるための判断基準として、実際のケーススタディを紹介します。
例えば、建設現場で大工として活動する個人がいるとしましょう。
この個人の業務日数を調べ、年間100日以上労働者を雇用しているかどうかを確認することが一つの目安になります。
また、労災保険に特別加入しているかどうかも、一人親方であるかを見分ける際の重要な要素です。特に、建設業界では労災への加入が求められるため、加入状況をチェックすることが推奨されます。
見極めの際は、個人が組合に正規に加入しているか、またその組合が法的に承認されているかを確認することも大切です。
これにより、一人親方であることを確認し、さらなるリスク管理につなげることが可能です。
まとめ
知識の重要性とリスク管理の必要性
一人親方としての活動は、自らの事業を主体的に運営するための方法として非常に有効です。
しかし、その独立性ゆえに、多くの責任とリスクが伴います。
特に、建設業界では一人親方と偽装一人親方を見分けることが重要であり、そのためには基本的な知識と判断基準を持つことが求められます。
一人親方としてのメリットは、労災保険に特別に加入することが可能である点です。
しかし、これを活用するためには加入のための条件を理解し、適切な手続きを行う必要があります。
また、万が一の場合に備えた保障の確保や、病気や怪我による収入の途絶えを防ぐための計画も重要です。
一方で、偽装一人親方であると判断された場合、社会保険の未加入によるリスクや法的な問題が生じる可能性があります。
これらのリスクを避けるためにも、法律やガイドラインに従った正しい処理が必要となります。
一人親方としての正確な見極めとリスク管理を行うためには、関連する法制度の理解だけでなく、実務経験に基づいた知識も重要です。
これらを基に、適切な働き方を選択し、安定した事業運営を目指すことが求められます。
中小建設業事業主の特別加入制度 3つの特徴!

業界最安水準
年会費36,000円
- 2000年以来の年会費業界最安水準
- 更新手数料無料 年会費のみ
- 労働保険事務組合が運営

最短翌日から加入可能!
加入証明書即日発行
- 簡単に加入可能!
- WEB、FAX、郵送、来所対応!
- 社労士賠責加入済み

3人の社会保険労務士常駐!
社労士賠償責任保険加入済
- 労災事故の安心!
- 労災請求の事務手数料一切なし
- 社会保険労務士報酬無料!
特別加入の手続き
中小事業主↗
労働保険事務組合を通じて「特別加入申請書(中小事業主等)」 を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し 、その承認を受けることになります。
※労働保険事務組合は全国に9,224団体あります。(令和4年3月現在)
一人親方 ↗
特別加入団体を通じて「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
※特別加入団体は全国に3173団体あります。(令和2年現在)
お問い合わせ・お申込み
- ※元請工事のない事業所のみとさせていただきます。元請工事がある事業所はお受けすることができません。
- ※雇用保険関係の手続きは原則行っていません。ご相談ください。
- ※社会保険労務士報酬は、いただきません。
- ※会費を安くしていますので、一括払いのみとさせていただきます。